技術者向けのプリント基板入門書を探しているなら、この本がおすすめです。
プリント基板設計の基礎』 を分かりやすく解説した1冊です。 これまでトランジスタ技術で紹介されてきた「プリント基板講座」がしっかりまとまっています。
初心者はもちろん、ある程度経験を積んだエンジニアにとっても、改めて基礎を体系的に整理できる良書です。
基板設計に携わるすべての技術者にとって、必ず役に立つ知識が詰まっています。
『技術者のためのプリント基板設計入門』は、プリント基板の基本構造や設計の流れ、さらに実際の設計手順までを、図や具体例を交えながら丁寧に解説しています。
理論と実践のバランスが取れており、「読むだけで理解できる」ではなく、「実際に手を動かして身につけられる」内容になっているのが特長です。
図面の描き方やCAD操作のコツ、さらに設計の意図を反映させるための考え方まで踏み込んで紹介されており、実際の現場で即使える知識を得ることができます。
また、これまで雑誌「トラ技」で連載されてきた基板設計講座をベースに、さらに加筆・再編集されて1冊にまとめられている点も魅力。
トラ技を愛読してきた技術者にとっては復習として、初めて読む方にとっては実践的な学びの入り口として活用できる構成になっています。
経験者であっても、新しい発見が得られるほど内容は濃く、基礎理論から応用設計までしっかりカバーしています。
PR
本の特徴と学べる内容
本書では、プリント基板の構造や設計の流れに加えて、実際の設計現場で役立つノウハウがたっぷり紹介されています。
単なる理論書ではなく、実務に即した視点で書かれているため、読んだ内容をすぐに自分の設計に取り入れられるのが魅力です。
さらに、設計に必要な基礎知識を体系的に学べるよう構成されており、初めて設計に挑戦する方でも理解が深まりやすい工夫がされています。
たとえば、パターンの間隔やライン幅、スルーホールのサイズなど、具体的な数値を交えて解説されており、初心者がつまずきやすい基礎的な部分から、ベテラン設計者でも見直したい応用テクニックまで幅広くカバーしています。
さらに、基板の材質選びや層構成、信号の引き回しにおける注意点など、現場での失敗例を踏まえた実践的なアドバイスも充実しています。
各テーマには図表や写真も添えられており、文字だけでは理解しづらい部分も視覚的に把握しやすい構成になっています。
また、製造段階を見越した設計上の工夫や、コストを抑えるためのポイント、品質を保ちながら歩留まりを上げる設計の考え方なども紹介されているため、単に「描ける」だけでなく「使える基板」を設計する力が身につく一冊といえるでしょう。
実務経験が浅い方でも、この本を手にすることで基板設計全体の流れを俯瞰し、より自信を持ってプロジェクトに取り組めるようになります。
回路設計者にもおすすめな理由
特に注目したいのが、「なぜ回路設計者が基板設計をすべきなのか」という視点で書かれている点です。
著者は、回路設計と基板設計を分業にせず、同じエンジニアが一貫して行うことの重要性を丁寧に解説しています。
回路の動作を理解したうえでレイアウトを行うことで、信号品質の向上やノイズ低減、さらにはトラブルシューティングのスピードアップなど、数多くのメリットが得られることが紹介されています。
設計者が自らの意図を基板上に反映させることができるため、より精度の高い製品が実現します。
また、回路設計者が自ら基板設計を学ぶことで、製造現場とのコミュニケーションが円滑になり、より実践的な設計判断ができるようになる点も強調されています。
設計段階での意図を反映しやすくなり、完成度の高い基板が生まれるというわけです。
実際に、設計から製造までを一貫して理解している技術者は、問題発生時の対応力が格段に高く、チーム全体の効率も上がるといわれています。
回路設計の知識はあるけれど、基板設計までは経験がない方にとっても、図や事例を交えた解説によって理解しやすく、読み進めるうちに自分でも設計を試してみたくなるような内容になっています。
基板設計の入門書としてだけでなく、設計プロセス全体を俯瞰する視点を身につけるための一冊としても価値があります。
読み終えたときには、単なる知識ではなく「実際に設計してみよう」と思える実践力が育つ構成です。
章構成の紹介
本の内容は以下のような構成になっています。
全体を通して、初めて基板設計に挑戦する人でも自然に理解を深められるよう、基礎から応用までが段階的に組み立てられています。
- 第1章:回路設計者が基板設計を行う意義を解説。設計の目的や、回路と基板の関係、設計者が知っておくべき基本的な考え方を紹介。具体的なエピソードや事例も交えて、なぜ基板設計が重要なのかを実感できる内容です。
- 第2章以降:基板の基本知識、アートワーク、CAD設計手法などを順に紹介。レイアウト設計の流れ、配線のポイント、部品配置のコツ、設計ミスを防ぐチェックリストなども丁寧に解説されています。初心者がつまずきやすい部分には図や解説欄があり、理解を助けます。
- 中盤:中級者向けとして、電源・信号の分離設計、アナログ・デジタル混在設計、グラウンド処理など、より高度なテーマにも踏み込みます。実際の基板例を通して、トラブルを未然に防ぐノウハウを学べます。さらに、シミュレーションを用いた検証や、熱対策を意識した配置など、実践的なトピックも多数収録されています。
- 後半:高速回路設計、パワー回路設計、鉛フリーはんだへの対応方法まで網羅。EMI対策、熱設計、層構成の最適化といった実践的な項目も扱い、最終的にプロの現場で通用するスキルが身につく構成です。特に、近年注目される高速伝送ライン設計や差動ペアの取り扱いなど、現代設計に欠かせない内容もカバーしています。
このように、段階的に学べる構成なので、基板設計の流れをしっかり理解しながら、理論と実務の両面をバランス良く習得できます。
読者がどのレベルからスタートしても、確実にスキルアップできるよう設計されています。
現場で役立つ実践的な内容
設計基準や部品配置、配線方法、検証工程など、実際の現場で必要な情報が細かく掲載されています。
各章では設計の理論的な背景に加えて、具体的な作業手順や注意すべきポイントも丁寧に説明されており、実際の設計プロセスをイメージしながら学ぶことができます。
たとえば、部品配置に関しては熱対策や信号の流れを意識したレイアウト手法が紹介され、配線ではクロストークやインピーダンス制御に関する具体例も挙げられています。
また、検証工程についてもシミュレーションや試作段階でのチェック方法、製造段階での不具合回避策など、実践的な情報が豊富です。
さらに、現場でのトラブル事例や改善策も掲載されており、読者が同じ失敗を繰り返さないように配慮されています。
実際の設計現場で役立つヒントが多く、初心者が自信を持って設計を進められるだけでなく、経験者がスキルをブラッシュアップするのにも最適です。
設計ツールごとの特徴や使い方、チーム設計でのデータ共有のポイントなど、現代の設計環境に即したアドバイスも含まれています。
基板設計を始めたばかりの方から、より実務的なスキルを身につけたい方まで、幅広く対応できる1冊です。
経験を重ねるほどに新たな発見がある内容で、座右の書として手元に置いておきたくなるほどの充実度です。
購入情報と価格
価格は参考価格で2,420円前後です。書店によって若干の差はありますが、コストパフォーマンスを考えると非常にお得な一冊です。
PR
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要な通販サイトで購入できます。レビュー評価も高く、購入者からは「実践的でわかりやすい」「現場で使える知識が詰まっている」と高評価を得ています。
まとめ:基板設計の基礎をこの1冊で
プリント基板設計の世界に一歩踏み出したい方には、まずこの本を手に取ってみるのがおすすめです。
単なる技術書というより、学びのステップをしっかり踏みながら知識を積み重ねていけるよう構成されており、初めての人でも無理なく理解を深めることができます。
基板設計に必要な知識が一通り身につくだけでなく、設計者としての考え方や視点も磨かれ、設計を通じて「なぜそうするのか」を理解できる点が特に優れています。
さらに、各章で学んだ知識を実際の設計に応用するための演習や、実際に現場で遭遇する課題のケーススタディも充実しています。
これにより、読者は本を読み進めながら自然と実務感覚を養うことができます。
初心者から中級者までしっかり学べる内容で、基板設計の基礎を確実に身につけられる1冊です。
知識だけでなく「設計者としての姿勢」まで学べる点が特徴で、特に独学では理解しづらい部分を補ってくれる丁寧な構成が魅力です。
仕事での設計品質を向上させたい方や、新しいツールを学びたい方にとっても心強いサポートとなるでしょう。
これからのキャリアを支える強力なパートナーとして、長く手元に置いておきたくなる1冊です。



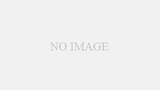
コメント